宝塚に住んで15年になります。
宝塚といえば宝塚歌劇。
 その日はとにかく席がよくて、
その日はとにかく席がよくて、
宝塚は新作主義といって基本的に一度やった舞台は二度やらないの
それ以来チャンスがあれば娘や家族みんなで観に行っています。
未体験の皆様、一度大劇場を訪れてみてはいかがでしょうか。
(ニュースレター2021年春号より)
数年前から話題の「線虫」を使うがん検査。
この線虫検査、尿一滴で、全身のがん(胃、大腸、肺、乳、膵臓、
*
立ち上げ当初は提携病院のみの取り扱いだったようですが、
大阪にも駅前に「N−NOSEステーションOSAKA」があり、
というわけで僕もさっそく線虫検査を受けてきました。
といっても、やることといえばキットを購入、

第一生命ビルの地下1階にあります
結果は6週間後で、6月ごろ判明する予定です(
もしも検査結果が「陽性」だったらと思うとドキドキものですが、
もちろん「低リスク」ならホッと一安心ですが、油断大敵。
*
今やがんは早期発見で治る時代です。
(ニュースレター2021年春号より)

大阪府立中之島図書館の桜(遠景は裁判所)
「沈黙の春」とは、1962年にアメリカで出版された生物学者レイチェル・カーソンの著作の題名です。カーソンは、この著作の中で、農薬で利用されている化学物質の危険性をとりあげ、それらによって鳥たちも鳴かない「沈黙の春」がおとずれると世に警告しました。しかし、今、世界は、農薬ではなくウイルスによって、鳥ではなく人間が押し黙る二度目の「沈黙の春」を迎えています。
日本では昨年1月に始まった新型コロナウィルスの感染拡大は、2年目に入った今も勢いはおとろえず、第三波が収まったと思ったらもう第四波の兆しが見られる状況です(4月12日現在)。
この自然からの侵襲に人間はなすすべもなく、1年目の昨春は、飲酒を伴う花見は各地で禁止となり、春の選抜高校野球は中止、プロ野球も開幕が6月にずれ込みました。
2年目の今春は、花見の禁止は変わらないものの、高校野球は予定通り開かれ、プロ野球も3月26日には両リーグとも開幕するなど、この歓迎されざる自然からの侵襲とのつきあいにも少しは慣れてきたように思います。
それでも、多人数が集まったり、懇親会を開いたり、孫が祖父母に会いに行ったりなど、これまで普通に行われていたことができないもどかしい状況は続いています。もしコロナの感染拡大に意味があるとすれば、そんな何でもない人の営みがかけがえのないものであることを我々に教えてくれたことくらいでしょう。
しかし、それももう十分です。ようやく始まったワクチン摂取の効果が出て、我々の生活が平常に戻ることを願ってやみません。それまで、皆様、お健やかにお過ごしください。
(ニュースレター2021年春号より)
事務所のこと | 2021年5月10日
こんにちは!相続アドバイザーでニュースレター担当の赤澤秀行です。
大阪では3度目の緊急事態宣言が今月末まで延長されました。一方で諸外国ではワクチンの普及とともに徐々に規制が緩和されています。半年遅れぐらいで日本も続くとは思いますが、7月にはオリンピックも予定通り開催することになってますし、まだまだ先が見通せない状況です。
そんななかですが、昨年はコロナで発行できなかった弊所の手作りニュースレター春号を先月末に無事発行することができました。いつもとあまり代わり映えしない内容ですが、ご笑覧いただければと思います。
弊所のニュースレターはこれまで当事務所とご縁のあった方々にお送りしておりますので、うちに来てないよ、という方はどうぞご一報ください。

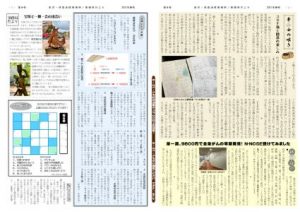
次号は8月末に夏号をお送りする予定です。どうぞお楽しみに!
なお、「読者の広場」コーナーでは、投稿を募集しています。ニュースレターの感想やご意見ご質問どしどしお送りください。その他、謎解き、川柳、似顔絵なんでもどうぞ!(*^^*)
事務所のこと | 2021年4月26日
緊急事態宣言により、こどもの発表会の無観客開催が決まりました・・・泣
保護者は1名のみということで、僕は家で留守番決定です。残念無念。
まあ発表会が中止にならなかっただけでも良しとしないといけませんね。
ほんま、コロナええかげんにしてよ、って感じです。
さて、弊所手作りのニュースレター「事務所だより」、今日プリント業者から印刷が届き、現在鋭意折りと封緘作業中です。今日明日で仕上げ、明後日には投函するのを目標にえっちらおっちら作業しております。
弊所ニュースレターの創刊は今から3年前、2018年の夏。年賀状と暑中見舞いは毎年送っていたものの、もう少し事務所の様子を楽しくお知らせできるものはないかということで始めたものです。
それ以来、これまでお世話になった方々、ご依頼者の皆様、その他関係者各位に、毎回5〜600部ぐらいの少部数ですが、正月(1月)・春(4月末)・夏(8月末)と、4ヶ月おきに年3回発行しています。
昨年の春は緊急事態宣言の影響で1回お休みしましたので、今回で第8号になりました。当初目標の10号まではなんとか続けようということだったので、あと2号、来年の正月には目標達成できそうです。それ以降は更にパワーアップして続けていければいいなあと思っていますが果たして。
ニュースレターの内容は、所員の近況報告やら法律のうんちく話やら、ランチ情報など雑多なもので、僕が最終的に原稿を集めて「パーソナル編集長」というWindowsのDTPソフトで仕上げています。
なんせ新聞づくりもDTPソフトも初めてなので、作成当初はいろんな資料を参考に四苦八苦しましたが、もともとモノ作りは好きなほうなので今は結構楽しんでやっています。もっとも、原稿を書かされる弁護士らは毎回苦労しているようですが(笑)。
印刷は事務所のカラーコピーで出すより断然安いネットプリントを利用しています。
現在ネットプリントの大手といえば「ラクスル」と「プリントパック」でしょうか。ラクスルも以前セミナーチラシなどで使ったことがあるのですが、現在はプリントパックで落ち着いています。
プリントパックは「クイックデータチェック」という入稿してスグにパソコンの画面で仕上がりが確認できるシステムがあり、これが非常に使い勝手がいいのと、発送も早く、仕上がりもまずまず。それでいて価格が安いのが魅力。折りA4両面カラー送料込みで600部8千円ちょっとです(納期7日の場合)。
ただ今回に限っていうとサイトの不具合か何かで「クイックデータチェック」の仕上がり確認ができず、サポートに何度も電話して、夜の10時ごろようやくつながってなんとか事なきを得たこと、印刷の仕上がりが珍しく悪く、1ページめにフォントズレが生じていたことが残念。
フォントズレはちょっとひどくて再印刷ものでしたが、4月中の発送を締め切りにしているため、返品再印刷は断念し、申し訳なくもそのままお送りすることにします。なんか今回は文字が荒れてるぞと思われるかもしれませんが(そこまでちゃんと読んでいただけているとありがたいです)、何卒ご容赦くださいませ(汗)。
一応プリントパックには品質改善の要望をだしときましたので、次回はきれいな印刷でお送りできると思います(たぶん)。もし次回もダメなら業者変更も検討しなあきませんね。
(追記)
プリントパックから連絡があり、今回のプリント料金はポイントで返還してくれるとのこと。誠意ある対応で安心しました。
事務所のこと | 2021年4月23日
当事務所には入り口奥にちょっとしたスペースがあり、倉庫として使っています。
奥は古い記録やらを収納しているのですが、空きダンボールの処理については長年適当に積み上げて、溜まったら捨てていました。
しかしどうも見た目も悪いし、ダンボールをゴミとして処分するときも余計な手間がかかる。
そこで、ネット情報をもとに、百均(ダイソー)で買える素材でダンボールストッカーを作ってみました。
部品はポール(47cm)4本と、棚(15*30)と、キャスター(2個入)2組と、ポール留め具(4つ入り)。8点で締めて税込み880円です。
これが

こうで

こうなります!

さっそく倉庫スペースに設置。

いい感じにダンボールをストックできそうです。
100均ダンボールストッカー、おすすめです。

皆様 明けましておめでとうございます。今年が皆様にとりまして良い一年となりますことを心よりお祈り申しあげます。
さて、日本の裁判にもっとITを導入すべきであるという意見は、実は、今のコロナ騒ぎが起きる前からありました。これまで、日本の裁判は、裁判所に原告と被告双方が出頭し面つきあわせてやりとりをするのが原則とされ、遠方の裁判所の場合などに例外的に電話会議が認められる程度でした。しかし、SNSが普通に利用されている現代にこれではあまりにも時代遅れだということで、Teamsなどのインターネットによる通信手段を利用して、例えば弁護士事務所にいながら裁判に参加する、場合によっては証人尋問をするようなことまで認めるべきだという意見が叫ばれていたのです。
一方、そのようにIT化を進めるべきであるという意見に対しては、公開の法廷で裁判を受ける権利を保障した憲法に違反するとか、証人の顔を直接見もしないような尋問では正しい事実認定はできないといった根強い反対意見もありました。
しかし、昨年にコロナ騒ぎが起きてからは、感染防止の必要から、裁判所が当事者になるべく裁判所に来ないように指示し、裁判の進行に関する打合せを電話会議で済ませることが多くなりました。また、我々弁護士も、弁護士同士の会議や依頼者との打合せなどをオンラインで行う機会が増えました。そのような体験をふまえての私の率直な感想は、今の程度であれば電話会議やオンラインでもさほど不都合はなく、かなりのことができそうだということです。
しかし、これがもっと事態が進み、証人尋問までもオンラインで行い、裁判官にも相手方の弁護士にも一度も会わないままに裁判が終わってしまうというようなことになればどうなのか、それが果たして裁判と言えるのか、疑問はぬぐえません。
「必要が制度を変える」と言われますが、コロナが日本の裁判をどこまで変えるのか、注意深く見守っていきたいと思います。(弁護士 井奥圭介)
(ニュースレター2021年新年号より)